みなさん、こんにちは!
グリーンフードの矢村です(*’ω’*)
日本の夏の風物詩といえば、やっぱり「土用の丑の日のうなぎ」ですよね。
この時期になると、うなぎ屋さんののぼりが立ち並び、
スーパーにも特設コーナーが登場します。
でも、そもそも私たちって、なぜこの日にうなぎを食べるようになったのでしょうか?
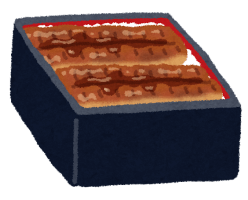
「土用」って、何のこと?
「土用」とは、立春・立夏・立秋・立冬といった季節の変わり目の直前、
およそ18日間を指す言葉です。実は季節ごとに土用は存在するのですが、
特に有名なのが「夏の土用」。
つまり、夏の土用の期間にある「丑の日」が、
いわゆる「土用の丑の日」なんです。
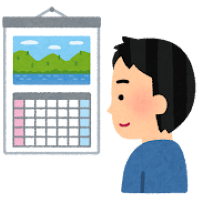
じゃあ、「丑の日」って?
「丑」とは、みなさんご存じの干支(えと)の「うし」のこと。
日付にも十二支が割り当てられていて、
土用の期間中に「丑」の日にあたる日が「土用の丑の日」になります。
年によっては、土用の間に丑の日が2回巡ってくることもあり、
その場合は「一の丑」「二の丑」と呼び分けられます。
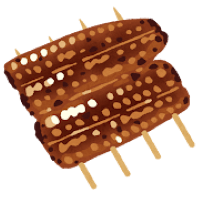
なぜ、うなぎを食べる習慣が生まれたの?
この風習が始まったルーツは諸説ありますが、
最も有名なのが平賀源内のエピソードです。
江戸時代、夏場にうなぎが売れなくて困っていたうなぎ屋さんから
相談を受けた源内は、「本日、土用丑の日」と書いた貼り紙を
店に貼るよう助言したそうです。
これが評判を呼び、以後、うなぎ=土用の丑の日という
イメージが定着したと言われています。
また、昔から「う」のつく食べ物(うなぎ、梅干し、うどんなど)を
食べると夏バテ予防になるとも信じられていました。
その中でも、栄養価が高いうなぎは、
まさに理にかなった夏のスタミナ食だったと言えるでしょう。

現代における「うなぎ」との向き合い方
近年ではうなぎに代わる食材で作った「うな重風」の料理や、
土用の日に「う」のつく別の食材を食べるスタイルも注目を集めていますね。
「土用の丑の日」は、単にうなぎを食べるだけの日ではなく、
季節の変わり目に体調を整えるための知恵の日とも言えるかもしれません。

今年の丑の日には、うなぎだけにこだわらず、
ご自身の体に合った“スタミナ食”を楽しんでみてはいかがでしょうか?
以上です!
それでは次回のGF便りもお楽しみに♪


