皆さん、こんにちは!
グリーンフードの矢村です(`・ω・´)ゞ
いつもご覧いただきありがとうございます。
今日は調味料についてお話ししたいと思います(*’ω’*)
11月3日は「文化の日」でしたが
「調味料の日」でもあるのをご存知でしょうか。
これは、伝統調味料を通して和食のすばらしさを感じてほしいという思いから、
日本野菜ソムリエ協会によって制定されました。
なぜ11月3日になったかというと、
「いい(11)味(3)」の語呂合わせや、和食文化を大切にしようという理由から
「文化の日」と同日にしたのが由来になっています。
★料理のさしすせそ
味付けをするときにこの順番通りに入れていくと美味しくなると言われていますが
いったいなぜでしょうか?
それは調味料の分子の大きさに関係しています。

★砂糖
分子が大きく浸透するまで時間がかかるため、
最初に使用するのが望ましいです。
砂糖には、料理に甘みをつけるだけでなく、
食材をやわらかくしたり防腐効果があります。
★塩
砂糖と比べて分子が小さく、染み込みやすいのが特徴です。
先に塩を入れると砂糖が浸透しなくなるため、2番目に入れるのがいいでしょう。
塩には食材のアクや水分、ぬめりを取る役割のほか、
食材をやわらかくしたり殺菌作用をもちます。
★酢・醤油・味噌
料理に風味や香りをプラスするため、
なるべく最後に加えると美味しく仕上がります。
お酢⇒ポーチドエッグを作るとき、お酢を入れますよね。
これは、お酢にたんぱく質を固める作用があるためです。
また、食材の変色を防ぐ効果があります。
醤油・味噌⇒食材の保存性を高めたり、臭みを抑制させる働きがあります。
★料理酒・みりん
お酒、本みりん→砂糖と同じタイミング
本みりんは、アルコール分と糖分を豊富に含んでいます。
砂糖と同様に、分子が大きいため味が染み込むのに時間がかかります。
また、アルコールには食材の臭みを消す効果や、食材を柔らかくする効果があり、
煮物などの場合は最初に加熱することでアルコールを飛ばし、
風味を良くします。そのため、砂糖と同じタイミング、
つまり料理の早い段階で加えるのが良いとされています。
料理酒も同様に、アルコールが食材の臭みを消し、風味を良くする役割があります。
また、肉や魚を柔らかくする効果もあるため、
下ごしらえや煮込みの早い段階で加えるのが一般的です。
みりん風調味料→最後が◎
みりん風調味料は、本みりんとは異なり、アルコール分をほとんど含んでいません。
代わりに、水あめやブドウ糖などの糖類や、うま味調味料などが主成分です。
加熱してもアルコールが飛ぶことがないため、主に料理のツヤ出しや照り出し、
風味付けを目的として、料理の最後に加えるのが適しています。
★体内への作用
▶砂糖
脳に効率よくエネルギーを送る働きがあります。
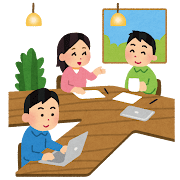
▶塩
ナトリウムは体液の圧力バランスを調整し、
神経細胞の信号伝達をサポートする役割があります。
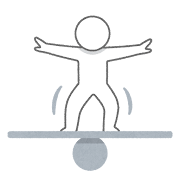
▶酢
クエン酸は疲労回復などに効果があるといわれています。
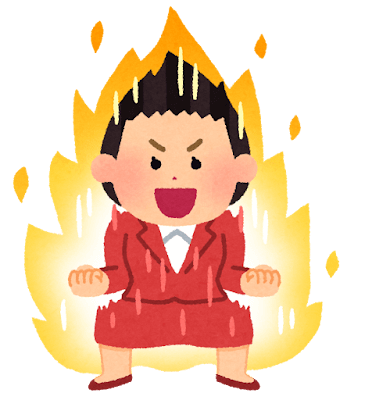
▶醤油
香り成分のフラノンは抗酸化作用があり、老化防止効果があるといわれています。

▶味噌
レシチン・サポニン→コレステロール値を下げ、動脈硬化や高血圧を予防
メラノイジン→血糖値の上昇を抑制
イソフラボン→更年期障害の緩和

★調味料〇✖クイズ
第1問:
濃い口醤油はうす口醤油より塩分が多い。〇か×か?
答え:✖
うす口醤油は濃い口醤油より食塩を約1割多く使用し、
発酵と熟成の速度を抑えることで淡い色に仕上げています。
【食塩相当量(100g当たり)】うす口→16.0g>濃い口→14.5g
第2問:
お酢はアルカリ性食品である。〇か×か?
答え:〇
主成分は酢酸なので、お酢は「酸性」を示します。
ですが、体内に入ると血液をアルカリ性にする作用から、
「アルカリ性食品」に分類されます。
いかがでしたでしょうか?
2問とも正解した方はもう立派な調味料ソムリエですね(*’ω’*)
それでは次回のGF便りもお楽しみに♪


