こんにちは!矢村です。
本日は今時期の田植えをメインにお米ができるまでの順番をご紹介します。
★田植えの前に農家の方が何をしているのか
▶1月~4月(地域の寒暖差によって作業の時期が異なります)
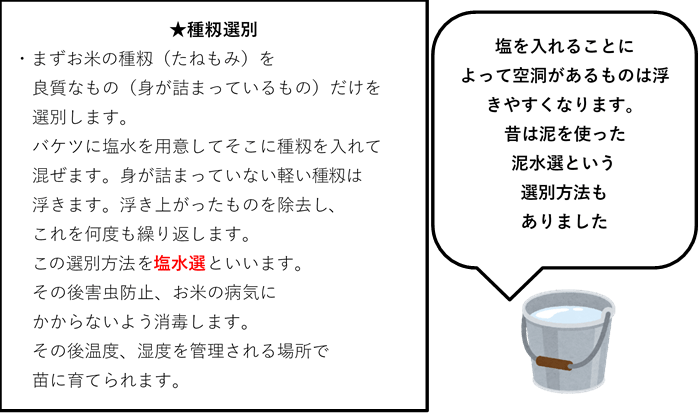
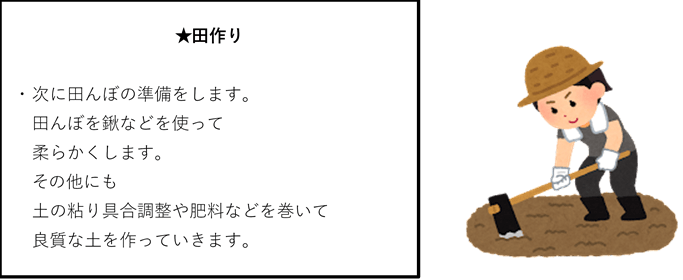
★田植え
▶5月~6月(地域の寒暖差によって作業の時期が異なります)
田植えは苗が密にならないよう、間隔をあけて植えます。
昔の方々は腰を曲げてひたすら植え続けていたので
「田植え歌」という仕事歌を歌いながら
みんなで田植えをしたそうです。
田植え歌には田んぼの神様を称えて、
無病息災、豊作を願いが込められています。
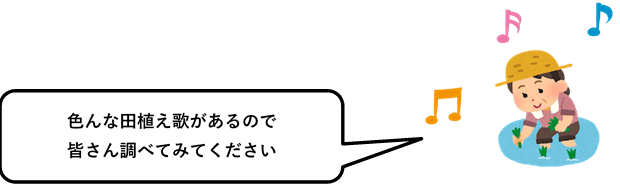
田植えが終わった後も、気候によって田んぼの水の量を調節したり
肥料を撒いたりしています。田んぼに合鴨を放って、合鴨に苗についた害虫や
雑草を食べてもらいます。
さらに合鴨が田んぼの中を泳ぐことによって
田んぼの土をかき混ぜてくれます。苗が育って穂がつく頃に田んぼにいる鴨を戻して、
水を抜いて稲狩り前の準備をします

★稲刈りから食卓に到着するまで
▶8月下旬~9月上旬(地域の寒暖差によって作業の時期が異なります)
稲刈りは穂がついて40~45日後を目安に行います。
その後稲を十分に乾かした後、稲から籾殻(もみがら)を取り出す
脱穀(だっこく)を行います。

▶籾殻から精米まで
籾殻は昔江戸時代は臼や杵を使って
籾殻の表面を除いていました。これを籾すりといいます。
籾からの表面を取り除いたものが玄米です。
そこからさらに表面の糠(ぬか)を除いたものが
精白米になります。
そのあと様々な安全管理の検査を通って
私たちの身近なスーパーなどに並びます。
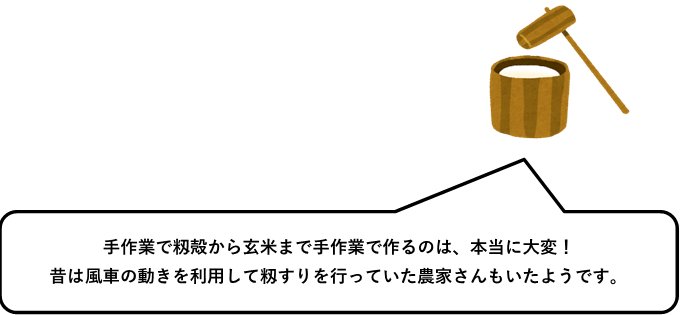
お米の栽培はこれを毎年必ず行っています。
去年は大雨と高温による供給不足やインバウンドによるお米の需要増加の
影響で一部の地域や銘柄で品薄状態が見られました。
美味しいお米が沢山実るように
農家の方たちは日々頑張っております。
皆様、ご飯は一粒一粒大事に食べましょう。

以上です!
それでは次回のGF便りもお楽しみに♪


